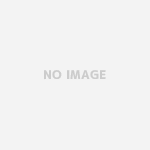【定期テスト】と【模試】の違いを脳のメカニズムで考える

定期テストでは点数が取れるのに模試では点が取れない人がいます。あなたはどうですか?
よく定期テストで点数が取れるのに模試で点数が取れない理由に、
定期テストでは、試験範囲がある
模試では、範囲があるようでない
という特徴が指摘されます。確かにそれも一理あるのですが、もっと決定的な違いがあります。
私が思う定期テストと模試の違いとは、
短期記憶と長期記憶の違いなんです。
今回はじめて出てきた単語がありますので説明しますね。
短期記憶とは、人が何かを覚えるときに一番はじめに覚える記憶形態のことです。
短期記憶ではまず、脳の「海馬」と言われている部分で記憶されます。
この海馬に記憶があるうちは、脳内ではその情報を「捨てるのか捨てないのか」を迷っている段階だと思ってください。
一方、
長期記憶とは、海馬で情報が必要と判断されたものを「側頭葉」に長く記憶する記憶の形態です。
この側頭葉に記憶することができてしまえば記憶が定着したとも言えます。
そして、この考え方を定期テストや模試や試験に当てはめると、
定期テストで要求されるのは、短い期間での短期記憶の集合体
模試や試験で要求されるのは、長い期間での長期記憶の集合体
ということになります。
定期テストは、試験範囲が2、3か月くらいの短い期間での勉強の集合体(習熟度)を確認したいんですよね。
一方、例えば3年生の模試では1年生からの学力が要求されているんですよね。3年生になって1年生からの学力を求めるって期間が長いですよね?
つまり「要求される期間の違い」と「要求される記憶形態」のこのギャップが、定期テストと模試の点数に差が出てしまう要因になってしまったわけです。